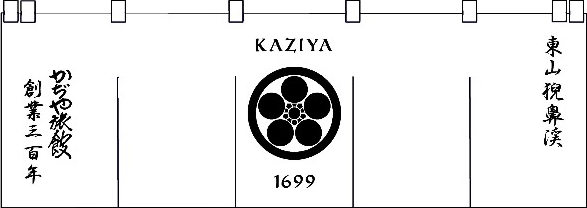平泉の冬の行事と言えば、絶対一度は見てほしいこれ。
こんにちは。初めまして。
今回は18代目に代わりましてブログを更新いたします。
この度、かぢや別館らまっころ山猫宿でお世話になることになりました、千葉 信子と申します。
急に現れまして、「あなた、何者?」ですよね。わかります。わかります。
簡単に自己紹介いたしますと、東日本大震災後、縁あって一関に移り住むことになり、その後3年半、NPO法人に所属し、岩手県陸前高田市や宮城県気仙沼市でコミュニティ支援をしてきたのですが、法人が活動を収束することになり、転職。その後1年2か月エフエム岩手平泉支局でリポーターをしておりました。しかし、不幸なことに支局が閉鎖になり(今は再開しております)、転職先として40歳過ぎで初めて旅館業に飛び込み、12月より、こちらでお世話になることになった次第。
だらだら書きましたが、どっぷり陸前高田に、どっぷり気仙沼に、どっぷり世界文化遺産の街平泉に浸かった私が、レアでコアな情報を発信していきたいと思っております。
もちろん、かぢや別館らまっころ山猫宿のある、一関市東山のレアでコアな情報探しもする所存。
前置きが長くなりましたが、本日お伝えするのは大寒だった20日(土)に行われた『もうつうじはつかやさい』について。
なぜひらがなで書いたかというと、はっきり言ってしまえば、これを音で聞いたとき、
「え?なんの野菜?」
と、内心思ったからです。ええ。私が。

また「もうつうじ」も旅館業で働いている経験から、正しく書いてもらえない、読んでもらえないお寺という認識。
で、漢字で書くと「毛越寺二十日夜祭」
このお祭り、事前取材を重ねる中、実際に当日を迎えるまで、全然イメージが出来なかった。
いくら聞いても、深く取材しても、過去の写真を見ても。
なぜかと言うと、毛越寺は毛越寺でこの日のために準備を重ね。
町民は町民でそわそわと、ものすごい準備を始めるから。
この日にぶつけてくるエネルギーとか、町民から感じられるこの行事への愛情たるや、一言じゃそりゃ言い表せない。
さらにお寺の行事である故、使われる言葉も難しい。
ただ、今回は難しいことは抜きで、ぜひ来年、見て感じて、知って納得してもらいたいので(出来たら当館に泊まって)できるだけ簡単な言葉でお伝えします。

『毛越寺二十日夜祭』は毛越寺の視点で言えば、14日から1週間行われる新春の祈祷、常行堂(じょうぎょうどう)の摩多羅神祭の最終日に執り行う祈祷。
最終日のことを滞りなく行い終えたという意味合いで「結願(けちがん)」と言います。(私は個人的になんだかこの言葉が好きです。けちがん)
この日、摩多羅神にお供え物をしたり、大々的な祈祷が行われたり、最後には舞を奉納したりする。
これが、毛越寺の視点。
では町民の視点ではいかがというと、厄年の老若男女が松明の灯りを先頭に町内から毛越寺常行堂まで練り歩き、供物などを宝前にお供えし、無病息災・家内安全などを祈祷する献膳行列を行う、蘇民祭。
そして数えで42歳の厄年の男たちは、下帯姿で松明をもって行列する。
下帯って。なに?

こんな感じです。
町内各所やお隣の奥州市衣川区から、ご近所を練り歩いた後、平泉駅の集合し、そこから毛越寺に向けてこのように行列します。
寒いです。
私は、極度の寒がりですが、長袖3枚にコート。ズボンも2枚着用に貼るカイロ3個装備でも寒いです。
なにせ大寒ですから。
それなのにこの格好。
で、毛越寺に入ると。

松明に火が灯され、「よーっ」という掛け声とともに、振り回します。
結構、危ない。
なので、このお祭りを支える数多くの、平たく言えば「ボランティア」が多くいます。
ちなみに、赤い鉢巻をしているのが厄年の男たちで、それ以外はすべて、そのボランティア。
そう、ボランティアも祭りを盛り上げるため「脱ぎます」
で、私もカメラは結構好きなのですが、このお祭り、カメラ好きにはたまらない、躍動感あるお祭り。
ゆえに、危険も顧みず、飛び込んでしまう人も多くて、その、ボランティアたちに「あぶねーぞー」とつまみ出されます。
私も結構近くまで寄って、写真を撮るのですが、装備が大したことないのと、小さなおばさんゆえ、「旦那さんか親戚が出てるんだろう」くらいの感覚なのか、つまみ出されないのだけど。
で、向かうは常行堂。

常行堂は本堂から見て、大泉が池を挟んだ対岸にあります。
そして、厄年の男たちが「よーっ」っと松明を振り回しつつ向かっている間、常行堂はというと。

42歳の男の厄年以外の厄年の人たちが供物を奉納し、それ以外にも町民ばかりではなくたくさんの観光客が集まっています。
その理由は、これからが祭りのクライマックスだから。
42歳厄年の男たちが常行堂に到着すると・・・。

掛け声とともに一斉に常行堂内に入り、
しばらくすると・・・。

蘇民袋を抱えた男が常行堂を飛び出し、厄年の男たちが後を追い。

蘇民袋争奪戦開始!
これが、流血するほど激しい。けんかになるほど激しい。
その死闘を勝ち抜くと。

こんな風に英雄になる。
蘇民袋の争奪戦に参加できるのは一生に一度。
家に蘇民袋があると聞くと「すげー」となる。
今年は、奥州市衣川区参加の方が、英雄になりました。
そして、みんなのお目当て餅まきへ。

撒いている餅は、町民が町内各所で搗いて準備したもの。

餅まきが終わると、今度は常行堂で、毛越寺僧侶による、『延年の舞』の奉納が行われます。
舞は、夜遅くまで続くのですが、これは、摩多羅神に奉納する舞なので、人間(観客)には背を向けて舞います。
『延年の舞」自体は藤原まつりなどで、見ることが出来るのですが、これは、観光客を向いて舞うので、二十日夜祭の『延年の舞」はとても貴重な体験です。また本来、『延年の舞』とはそういうものなので、厳かで素晴らしいです。
全部を見ることはできませんが、最初少しなら一般の方も見ることが出来ます。
これが、毛越寺二十日夜祭。
お分かりいただけたでしょうか?
そう。わかんないんですよ。
実際に見て、体験しないと。
だから来年はぜひぜひ。
とてつもなく寒いので、山ほど着込んでお越しください。

見ている人を元気にさせるものというのは、その物事に対して、愛情深く接し、精いっぱいで、一人じゃ成し遂げられず、そんな色々を感じさせるものであるんだな。
そんな風に、毎年行って思うお祭りです。
ちなみに、今年はたまたま、土曜日開催だった、二十日夜祭。
毎年20日にやりますし、21日は祝日でもなんでもないので、
この格好で何時間もうろうろし、散々酒を呑まされ、最後は死闘を繰り広げたとしても。
大体は、翌日容赦なく、仕事です。
働き盛りの42歳ですからね。
そんな容赦ないところも、含めてなんだか私はこのお祭りが大好きです。
来年はぜひぜひ、当館にお泊りの上、『毛越寺二十日夜祭』見て触れて感じて納得してみてはいかがでしょうか?
投稿者プロフィール

【東京からUターンして気が付いた地方生活の魅力】
【感じた事、考えたこと】
を綴ります。
平成3年5月25日生まれ。
高校卒業後、エコール辻東京に進学し「株式会社ひらまつ」で4年間調理場で修業。
その後、ビジネスマネジメントを学び実家の旅館に戻る。
趣味は、写真 生け花 料理。